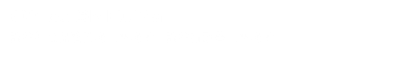社労士的日々
介護 僕は今なお発見し続けている
育児・介護休業法の改正に伴い、介護離職に関するニュースや報道を何回か見かけた。介護休業の取得率が低いこともあり、制度の周知や積極的な取得の働きかけが行われている。
現状の介護休業は、介護体制構築休業とでも名称を変え、別途、少なくとも1年間の介護に専念できる期間としての休業制度を設けるべきだと思う。
介護はした方がいい。するべきだとも思う。人の老い、あるいは人の死とじっくりと向き合うことができる。介護を担う機会があるにもかかわらず、それをしないことを、僕は許したくない。ましてや、若い人に押し付けてもならない。
僕は、親の介護は終えたが、僕なりのアプローチをもって、介護に取り組んでいる。根底にあるのは、喜んで欲しいという気持ち。
「これって、介護だよな」
そう思う場面に出くわすこともある。それは同時に、発見でもある。僕は今なお、発見し続けている。(2025.4.12)
話は尽きることなく
先日、90歳になるひとり暮らしのお年寄りのマンションを訪ねてきた。いつも2時間以上は話す。人の一生、「作品」だと思うと、会話は尽きることはない。ケーキ、ごちそうさま。次回はご飯を食べに行こうと約束して帰ってきた。どこまで関われるか、難しい問題もあり、また、僕が出しゃばって勝手に話を進めるわけにもいかない。ゆっくり、ゆっくり、「作品」を閉じることができれば、それでいいと思う。(2024.5.11)
どっぷり社労士
この1か月ほど、どっぷりと社労士業務。そんな最中、パソコンの不調。またしてもWindows Updateの更新エラー。幸い、土曜日を使って2日ほどで修復できたが、パソコンが正常な状態でないと、気分的にも仕事がはかどらない。2日続けて終電で帰った。帰宅が上り方向になるため、終電が意外と早い。
優先順位の低いものが、ますます手つかずになってしまっている。さて、明日も雨かな。今週は寒い日が続くらしい。それでも、また明日から頑張ろう。(2024.2.21)
私も行く(行かないで)
駅近くのグループホームのわきを通る度、いつも窓越しで手を振りあっていたお年寄りの女性。ホームの都合、あるいは体調の関係でひなたぼっこをやめてしまったのか、また、親の入院や死去に伴い、僕が通りかかる時間帯が変わってしまったこともあり、夏以降、顔を見かけることがなかった。ずっと気になっていた。元気にしているかなと。
年末、たまたまホームのスタッフの人が別のお年寄りと散歩をしているところに出くわした。そのお年寄りとも、時々手を振り合う仲で、やはり久しぶりだったのだが、僕のことを覚えていてくれた。その際、スタッフの人に聞いてみた。
「もうひとり、いつも窓辺のソファで休まれていたおばあさんがいらしたんですけど、元気にされています?」
寒くなって、ひなたぼっこをやめているとのことだった。そんなことがあったせいか、正月の元旦、事務所へ行く用事があり、いつものようにホームを通りかかったら、しばらく顔を見なかったお年寄りの女性がひなたぼっこをしていた。何か月ぶりだろう、5か月ぶりくらいだろうか。もしかしたら、年末のことがあって、スタッフの人がひなたぼっこの時間を設けてくれたのかもしれない。
手を振りあい、嬉しさも手伝い、窓越しに話しかけてみた。
「元気にしてた? ひさしぶりだね」
彼女も喜んでくれた。そればかりでなく、身体を前のめりにさせ、窓に手を寄せる。
「元気そうだね。よかった」
「どこ行くの?」
「うん、仕事に行ってくる」
「私も行く」
「うん、また来るね。明日も来るね」
窓越しの会話のため、加えて、おそらくははっきりとしゃべることが難しいのだろう、うまくは聞き取れなかったが、彼女はかぼそく絞り出すような声で確かに「私も行く」と言ったように聞こえた。それは、「行かないで」の意味であるかのように。
「また来てね」
泣いていた。涙を手で拭っていた。まるで小さな子供、窓越しに僕にすがってこようとする。
5か月前よりも、少し呆けた表情をしているように見えた。やっぱり施設は寂しいよなと思う。正月といえども、家族は来なかったのかもしれない。訪れていても、おそらくはすぐに帰ってしまったのだろう。
私も行く。施設ではなく自分の家に住んでいたら、その言葉は出てこなかったに違いない。今度、一緒に散歩にでも行けたらいいなと思う。お互い、名前も知らない。もしかしたら、僕のことを家族の誰かと思っているのかもしれない。泣かれると、ちょっと辛かったりもする。
この文章を書いているところで、石川で大地震のニュース。辛いよな。
人は死んだらだめだ。
今、僕が作っている曲。俺はまだ生きている。
先月のクリスマス、埼玉のお年寄りの女性のマンションを訪ねてきた。九十歳、一人暮らし、子供はいない。
「ごめんなさいね。世間話をしにわざわざ遠くまで来てもらって」
「いいのいいの。世間話をしに来たんだから」
おそらくは、多少認知症も始まってしまっている。以前、ケアマネさんに部屋の物を盗まれたと思い込んでいて、施設には絶対に入らないと言い切っている。幸い、大阪に住むめい御さんが一緒に住もうと言ってくれている。めい御さんはご主人と暮らしている。上手くいくことを願うしかない。
帰り際、握手をして別れた。
ありがとう。こちらこそ。また会おうね。
年末、知り合いにニーナ・シモンのCDを渡した。
「自分の葬式で一枚CDをかけるとしたなら、このCD」
寂しいとき、落ち込んだとき、聞きたくなる。そんな気持ちを吸収してくれる。吸収してほしくて、人はニーナ・シモンの歌を聞く。
僕が背負っているものは、ちっぽけなものでしかないが、それでも、僕もまた吸収することを意識していたい。
年明けの挨拶に代えて。(2024.1.1)
僕のバランス
日もすっかりと暮れ6時頃になると、介護を担っていた時のように、そろそろ帰らなければと思い、仕事がまだたくさん残っているにもかかわらず、僕は事務所を後にした。
介護と仕事、自分に負けたくないと思い、意地にもなっていた。家から事務所まで片道1時間、さすがに1時間程度しかいられないような日はともかく、たとえ2、3時間でも事務所にいられるのなら、無理をしても仕事に行っていた。土曜、日曜も同様。休みたくはなかった。
葬儀を終え、昨日今日、もちろん、時間的に余裕があるとはいえ、特に無理はしていない。介護をしている時も、意地になってまで事務所には向かわず、もっと家にいてあげればよかったと思うものの、介護を担っている間は、介護にだけ生きているわけではないと、僕は仕事をこなすことでバランスを保っていた。今は、バランスを取る必要がないだけのこと。
一方で、ムキになっている自分は嫌いではない。むしろ、僕らしかったりもする。介護を終えたからといって、いきなり介護前の感覚や生活に戻れるわけでもない。実際、仕事がなかなか手につかない。
さて、僕はどのような生き方をすることになるのだろうか。つまりは、介護を通して得たものが、どのような形で昇華されるのか。介護を通して、自分が変わったことには気づいている。(2023.10.27)
受け入れ難くとも、受け入れなければならぬもの
今日こそは休んで家でのんびりしていようと思っていたが、結局、休まなかった。休んでも問題なかったが、休むのをよしとしない性分。さぼったような気になってしまうから。
当初、「負けるもんか、負けるもんか」と思って介護と仕事の両立を図っていた。最近は少しばかり変わってきたのか、やるべきこと、やらなければいけないことをひたすらこなしていくような日々。
儲かるからこの仕事をやる、そういった感覚で仕事を選んだことがない。介護や福祉の業界の一部で、そんな感覚が垣間見えてしまった時、そのサービスを受けるのが嫌になる。これもまた、性分かな。即ち、受け入れ難くとも、受け入れなければならぬもの。(2023.10.2)
楽になれる日など来やしない
今日乗り越えれば明日楽になれる、明日乗り越えれば、次の日楽になれる。そんな日々。けど、明日になれば、あるいはその翌日になれば、また新たにやらなければならないことが持ち込まれる。結局、楽になれる日など来やしない。まぁ、そんなもんだ。疲れてはいるけどね。(2023.9.26)
年だなぁ、参った。
ここ2週間ほど、パソコンの不調に悩まされていた。Windows Updateの更新エラー。OSをインストールし直し、一度は直ったが、その後、再度不調に。面倒なので買い替えようと思っていたが、ディスクのクリーンアップなどを実施したところ、どうやら改善された模様。パソコンが快適に動くと、仕事もはかどる。不調の際、Edgeが立ち上がるのに10分以上時間を要していたので、インターネット一時ファイルが削除されて、調子がよくなったのかもしれない。そもそものWindows Updateの更新エラーもEdgeに関係していたとの話もある。
さて、その後、やってしまった。パソコン…。
キーボードのパッド部分にコーヒーをこぼしてしまった。口に含んでいたコーヒーを…。
今まで、コーヒーや紅茶などを飲む際、パソコンには絶対にこぼさないようにしてきた。実際、パソコンを使い始めて30年以上になるが、今まで一度も水をこぼしたことがない。よだれくらいはあるが…。
というか、今回もよだれのようなもの。近頃、さらに目が悪くなり、パソコンを長時間使っていると、パソコンの文字が見えづらくなり、眼鏡を外してパソコンの画面に食い入るようにしてキーボードを打つことがある。その時もそうだった。眼鏡を外し、パソコンの画面に食い入っていたところ、口元が開いてしまい、口の中に含んでいたコーヒーがひと口分、こぼれてしまった。
幸い、今のところ、パソコンは正常通りだが、ちょっと焦った。万が一、水漏れなどで故障した際の保険に加入してはいるが、修理に出すとなるとやはりそれなりに面倒だ。年だなぁ、参った。(2023.9.4)
まぁ、いいか。
Windows Updateの更新に失敗したのが先週の火曜日。6日目の日曜日、ようやくパソコンの修復及びWindows Updateの更新に成功。その日の夜も帰宅は遅くなったが、それでも久しぶりにすっきりとした気分で家へ帰ることができた。翌月曜日は、やっとまともな時間に帰宅。食事も久々にまともに食べた。一年に数回、こんな目に遭う。親の入院とパソコンの修復で終わった僕の盆休み。雨でびしょ濡れにもなったっけ。ただ、OSのインストールを待っている間など、読書は十分にすることができた(八十年現身の記/榛葉英治、これを読んだら満州脱出/武田英克も読みたくなった)。まぁ、いいか、と思うことにしたい。(2023.8.21)
僕は何か悪いことでもしたのか。
土曜から日曜にかけて、親の体調が悪化した。翌月曜日、看護師さんがやって来て、おそらくは誤嚥性による肺炎を起こしているだろうから、救急車を呼んだ方がいいとのこと。病院に搬送され、そのまま入院。やはり誤嚥性肺炎。昨日のことだ。
今日、面会に行き、様子を見てから事務所へ向かった。面会が可能な時間は14時から16時。僕にとっては中途半端な時間帯だ。しばらくは、14時に面会に行き、16時過ぎから事務所で仕事という日々が続きそうだ。自ずと、帰る時間が遅くなる。今日はパソコンの不調。アップデートでエラーが生じた。いろいろいじっていたら、23時近くになっていた。終電を乗り過ごさずに済むところで切り上げ、帰宅。ところが、電車を降りるとゲリラ豪雨。小1時間も待てば止むのだろうが(実際、1時間ほどで止んだ)、その1時間を待つのがもったいない。折りたたみ傘を持っていたが、それでもビショ濡れだ。あと30分でも早く事務所を出て入れば、こんな目に遭うことはなかった。僕、何か悪いことでもした?
親が入院することになって、
「息子さん、少しは楽になりますね」
と、ある介護関係者。いや、実際はそんなことない。日付がちょうど変わった頃、食事をしたが、この日、帰宅するまで朝から口にしたのは家を出る前に食べたドーナツ1個だけ。つい先日まで4キロ減だった体重も6キロ減となった。今ももう深夜3時を回っている。
退院後は、訪問診療に切り替える予定。今、その手続きを行っているところ。介護サービスの内容やスケジュールも組み直さなければならないだろう。さてさて。(2023.8.15)
明日、楽をしたいがために、今日、無理をする。
今日こそは、ゆっくり、じっくり仕事に取り組みながら過ごせるなと思った日に限って、面倒くさい雑用が飛び込んでくる。なかなか頭の中がすっきりしない日々。休みが大事だということもわかっているが、休みたいわけではない。明日、楽をしたいがために、今日、無理をする。(2023.2.20)
僕はどうやら歯を食いしばっているらしい。
歯痛(奥歯)がするため、定期検査の際、診てもらった。虫歯ではなく、おそらくは「食いしばり」によるものとのこと。この「食いしばり」、多くの場合、ストレスが原因らしい。近頃、とにかく時間に追われている。おまけにここ数日は、コロナワクチンの注射の副作用も加わっている。僕はどうやら、歯を食いしばっているようだ。
仕事からの帰り道、塾があるビルに女の子が走って入って行った。その際、マフラーを落としていった。
「お姉ちゃん、落ちた、落ちた」
僕は教えてあげた。あとで思った。彼女は受験生。「落ちた、落ちた」はまずかったよな。せめて、「落とした、落とした」だったかなと。どっちも似たようなものかな。
ここ数日、イレギュラーなケースの案件で難儀していた。なかなか楽にはならないようだ。楽にしてしまってはいけないこともあるということなのだろう。(2022.12.18)
戦っている。
「戦っているのがわかる」
ある人がそう言ってくれた。わかってくれていると思うと、嬉しかった。そう、僕は戦っている。そして、やはり戦っている人を応援する。(2022.12.3)
続けると、僕は決めている。
何の話をしていても、介護と結びつけることができたりする。当然だろう、介護は生き方、死に方をテーマに含んでいるのだから。その日、話をしていたのは、人を楽しませることの大事さ。介護にも通じる。僕らは、与えておけばそれでいいと思いがちだったりする。施設に入ってもらえばいい、食事(弁当は最悪だ)を用意しておけばいい、と。だが、もちろん、それは見抜かれる。介護されている本人が不機嫌になるのも当たり前だ。いずれ介護は終わると、人に言われた時、僕は、「いや、続ける」と答えた。実は、次のお年寄りが控えている。続けると、僕は決めている。(2022.4.20)
法改正にあわせ就業規則他、各種規程改定
法改正にあわせ、就業規則や特定個人情報等取扱規程他、各種規程の改定終了。 「ふ~っ」と思わずため息。今年もそこそこ面倒な作業でした。(2022.2.10)
頭を丸めて出直せ
先日の新聞の読者相談の欄。親の介護を担っている姉、その姉が親の金の管理も行っているが、使い方に納得がいかず、どうしたらいいかといった妹からの相談内容。それに対し、回答者は、「介護を知らない無責任な人の放言」と一蹴、「頭を丸めて出直しなさい」と締めくくっていた。なんとも痛快。さて、恥を晒すようだがわが身内のひとり。ずっと前から気づいていたが、用もないのに僕のサイト(つまりこのページ)をほぼ毎日、詮索している。何が面白いのか。これを読んだらやめてほしいのだが。僕も言おう、頭を丸めて出直せ。(2022.1.10)
重い…。
多少は余裕を持てるようになったつもりだったが、そうでもなかったようだ。僕自身、僕はまだ大丈夫だと思っていたが、いつのまにかに無理をしていたのだろう。介護は重い。覚悟を試され、選択を強いられる。(2021.11.28)
ファイト
強がっているわけではない。いや、強がっているかな。毎日8時間から9時間(午前中6時間、夜2時間程度)、自宅での母親の介護を担っている日々。もちろん、穏やかな毎日であるわけがなく、時には声を荒らげることも珍しくない。それでも、介護を経験することができてよかったと思っている。経験していなかったら、介護を担っている人の気持ちが理解できなかっただろう。
もう7年ほど前のことになる。知り合いの高齢の男性が奥さんと義姉の2人の介護を担っていた。おそらく、相当疲れていたのだろう。夜中に突然お亡くなりになられた。僕は義姉から連絡を受け、駆け付けたが既に遅かった。日頃、もっと何かできることがあったのではないかと、今になって自分を責めたりもする。あの頃、介護の大変さを何もわかってはいなかった。
僕は、好きなことをして生きてきたと言えば格好良すぎるが、少なくとも嫌いな仕事に就くことはなかった。もちろん、個別には嫌な仕事を受けることはあっても、概ね、好きなようにやってきた。学生時代のアルバイトを除けば、人に雇われたこともなく、ずっとフリーランスでやれてこれた。
今、僕が親を施設に入居させ、自分は以前のように仕事をしたとしても、存分には好きなようにはできないような気がする。はたして、ある意味、親を放り出し、自分だけが好き勝手にやっていいものか。そう思うのではないか。
そもそも、僕はまだ音を上げていやしない。負けたくはない。僕よりもっと大変な思いをしている人もいる。そして、何よりも、時に希望を感じられる瞬間がある。また、弟は介護を一切放棄、姉からも足を引っ張られるのは悲しいが、看護師さんたちの応援や友らからの励ましもある。くじけそうになると、いつだったか、駅の階段を障害のある小さな子供がおじいさんに連れられ懸命に上っていた時の表情を思い出す。ファイト。(2021.9.22)

外からの視線
一昨日、母親が退院して約3週間、初めて僕自身、夜中、まともに寝ることができた。けど、翌日からは再び、深夜の介助を余儀なくされ、熟睡には程遠い日々。
不平不満、愚痴を言うのは施設に入れようとしないおまえが悪いとばかりに身内(姉弟)から足を引っ張られ、たとえすぐ隣に身内が住んでいようとも、悲しいかな、身内ほどあてにならないものはないと実感。支えになるのは外部の人の励まし。訪問看護師さん、近所の母親の知人、僕の昔の連れ、などなど。
「在宅で介護しようとする気持ちは尊いものなんです」
と、ある看護師さんの言葉に救われたその日、おそらくこれは、身内であっても同居していなければわかってもらえないものなのだろう。
外からの視線は意外と大事だったりする。では、自分はどんな視線でもって生きているか。これを機に、ちょっと意識してみようと思う。(2021.7.12)
波と電車と社労士
先日、社労士試験合格発表。昔の知り合いが合格したとのこと。
「いい波乗ってる?」とはもはや誰も言わないだろうが、僭越ながら電話でこんな話をした。
「波に乗ることが大事。とりわけ、働き方改革。来年は同一労働同一賃金、均等・均衡待遇も控えているし。仕事の依頼があってから(波に)乗るようでは遅すぎる」
似たような話をするとき、僕は波を電車に置き換える。常に電車は走っている。けっして停車してはいない。法改正があるからだ。一番後ろの車両でかまわない。まずは電車に乗ることが大事。もちろん、何でも屋になりたいのならともかく、全ての電車に乗るのは無理。乗る電車は自ずと絞られてくるもの。依頼があって初めてその電車に乗ることもある。そのときは、最後尾から駆け足で先頭車両へ移動する。そんな、社労士的日々。(2019.11.9)
希望、軽々しいことなく
その日の面談、喋り過ぎたせいか、話を終え、喉が渇き切っていた。もし、へこんでいるのなら、少しでも希望を見出してもらいたい、そう思って臨むものの、所詮、僕はこの程度、軽々しく希望という言葉を口に出すべきではないし、ときには自分の無能さにも落胆しつつ、それでもやはり、諦めきれないものを持っている日々。胡散臭くはありたくない。堂々としているさ。(2019.11.1)
健康情報等の取扱規程
働き方改革に関連し、昨年、心身の状態に関する情報の適正な取扱いに関する指針が出され、また先月には、厚労省から手引き(健康情報等の取扱規程を策定するための手引き)とモデル就業規則(31.3版)も公表された。
さて、就業規則の作成や見直しにあたって、僕は細かいところも気にしてしまう。例えば、改正労働安全衛生法では「事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」と定められており、さらに「健康診断等に関する秘密の保持」も求められている。
ここで頭を悩ませたのが、文言の使い方。「心身の状態に関する情報」と「健康情報等」、手引きでは同義として扱われているが、単にすなわち「同じ」というわけではない。疑問に思う点を厚労省や複数の労働局に問い合わせてみたところ、明確な回答はなかなか得られず、ある局でようやく腑に落ちる説明をしてもらえた。
モデル就業規則(31.3版)では、「事業者は労働者の心身の状態に関する情報を適正に取り扱う」の一文のみの定めになっている。一方で、手引きでは、取扱規程は就業規則に記載することが望ましいと書かれている。では、実際のところ、就業規則にどのように落とし込んだらいいものか。
僕に限って言えば、今回の法改正においては、労働基準法よりも労働安全衛生法の改正に関する記載に難儀した次第。苦労した話は、無性に人にしたくなる。少なくとも今月いっぱいは、同業者と顔を合わせばおそらくはその話をしているに違いない。(31.4.15)
労働安全衛生法
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第104条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
(健康診断等に関する秘密の保持)
第105条 第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項の規定による面接指導、第66条の10第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
職業、社会保険労務士
職業、社会保険労務士。
この場合の「社会」とは、「社会保険」に係る「社会」なのか。いや、そうではなく、社会そのものであると考えたい。例えば「社会政策」における「社会」。
思えば、ずっと社会を意識し続けてきた。とりわけ30代、僕はひとつの社会を作りたかった。結果、失敗こそしたが、完全なる失敗かといえば、あながちそうでもなかっただろうと思っている。その後、地域に深く関わった。これもまぎれもなくひとつの社会。そして今、僕が身を置いている社会。ここもまた、話は尽きることなく。いやぁ、いろいろあってね。(30.11.9)
僕と話したらおもしろいよ
彼女、明らかに以前より明るい声でその後の経過を報告してくれた。全てが解決したわけではないが、それでもとりあえずは上を向いているようだ。
別の女性、どうやら最悪の事態は避けられそうな具合。安堵。
「僕と話したらおもしろいよ」
それは、僕と話せば、なんとかなることもいっぱいあるよ、そんな意味をも含んでいる。言葉は肉体。(29.12.7)
想像・イメージ
「人よりひどい目に遭うのが作家の使命」と、ある作家。僕の仕事と結びつけてみる。案件の内容にもよるが、相談者・依頼者の立場にどれだけ立って考えることができるか。ときには同様の立場になった経験こそなくとも、想像やイメージすることが求められることがある。その際、どれだけのことを想像、イメージすることができるか。微妙なギャップが実は相談者・依頼者にとっては大きなこだわりであったり、懸念していることに繋がったりもする。さて、僕のイメージ力。おそらく天下一品。(29.9.8)
厳しい暑さ
複数の年金事務所にある手続きに関して確認したところ、年金事務所によって異なる回答が返ってきたため、再度、詳しく確認することに。なるほど、そういう仕組みかと、理解するのに丸1日要した次第。多くの同業者が知らなかったことに違いない。というのも、年金事務所のある担当者が「このようなケースは今までに扱ったことがありません」と話すほどだから。いや、あまりにも簡単なことで、誰も聞かなかった? そういうわけでもないだろう、だったら、年金事務所によって回答が異なるはずがない。
それはそうと、事務所近くの八百屋に早くもスイカが並んでいた。今年の夏は例年よりも厳しい暑さになるらしい。といっても、毎年厳しい暑さが続いているような気もするが。(29.5.24)
労働協約は「法」か「契約」か。
社労士は学問的にもおもしろい。例えば、労働協約は「法」か「契約」か。僕はそんな話が大好きだったりする。先日もその話で盛り上がった。僕の方から振った話。さらに話は弾んで「労働協約の不利益変更」について。就業規則の不利益変更ではなく、労働協約の不利益変更であるところがこの話のミソ。気がついたら深夜2時を回っていました。終電を気にしなくてよかったので、ついつい深酒。弾けた夜に乾杯!(29.2.3)
個人事業主
ある新聞の特集記事。「土日は休みたい」「残業代もほしい」という社員の声を、経営者としての言葉であったが「泣き言を言う社員」という言い回しをしていた。社労士としての倫理観からは問題があるとも言えるが、例えば就業規則の作成において、経営者と労働者の感覚のギャップを埋める作業を要することがある。なお、先の記事は、その会社では10人ほどの技術者を個人事業主として独立させたことで、破綻を免れたというものだ。ただし、それは雇用調整が目的ではない。個人の原動力こそが求められているとの考えによるものだった。かくいう僕自身、仕事の内容こそ変われど大学時代から今に至るまで一貫して個人事業主。おそらく、あと20年ほど。(28.11.3)
ポケットティッシュに困らない街
街を歩いていて、声をかけられるパターンは2通り。
「すみません」
「こんにちは」
前者の場合、主に道を尋ねられる場合だろう。後者は、何らかの営業や宣伝が絡んでいることが多い。
さて、事務所の最寄り駅は西武新宿線花小金井駅。駅前で「こんにちは」と声をかけられた。スイーツの移動販売。さらに歩くと、再び「こんにちは」と声をかけられた。今度は「りんごジュース、飲んでいかれませんか」。いずれもふいを突かれたように声をかけられたので、少々驚いた。
ちなみに美容院のフライヤーは、渡されないことの方が多い。また、花小金井ではポケットティッシュに困らない。周辺で新築のマンション建設が複数棟予定されており、駅前でティッシュが配られていない日はない。とりあえず、こんな街です。(28.7.28)
就業規則と焼酎ロック
ある居酒屋。梅サワーに梅の実を加えたら100円プラス。この料金設定、いかがですか? まぁ、100円はちょっと高いかもしれないけど、仕方がない、そう思われる方が多いかと思います。では、焼酎。ロックの場合はストレートの料金に100円プラス。これはいかがでしょうか。ちなみにロックの氷は製氷機で作ったもの。それにレモンスライス(輪切りの半分の大きさ)が添えられています。これはさすがにどうかなと。ロック用のブロックの氷、あるいはレモン2分の1個を生搾りするのならともかく、ちょっと高いかなと。
さて、こんなことを気にしてしまうのは、性格ではなく、普段の仕事が影響していると思いたいのですが、これまたいかがでしょうか。例えば就業規則の作成。突っ込まれるところをいかになくすか、この観点は欠かせません。また、定めた理由、根拠は、明文化するかはともかく、少なくとも説明できるよう明確であることが求められます。他にも、契約書の作成も同様。
ちなみにその居酒屋、目当ての店がたまたま休みで、代わりに入ったお店。次はどうかな。(27.9.11)
常時十人未満の労働者を使用する使用者
労働基準法第89条にて、就業規則の作成及び届出義務につき、以下のように定められています。
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
また、第91条にて、制裁規定の制限の定めが下記のように定められています。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
では、常時十人未満の労働者を使用する使用者、つまり就業規則の作成及び届出義務がない事業所において、減給について雇用契約書で定めた場合、あるいは服務規程という書類等、内規として周知を行った場合、減給の定めは有効かどうか、検討を要すると考えられます。
あるいは、1箇月単位の変形労働時間制について、第32条の2において、以下のように定められています。
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
この場合において、常時十人未満の労働者を使用する使用者が就業規則(届出なし)にて1箇月単位の変形労働時間制を定めた場合、はたして有効かどうか、やはり検討を要すると考えられます。(27.9.7)
先生、脅かさないで下さいよ
「先生、脅かさないで下さいよ」
そう言われるときがあります。もちろん、脅しているわけではなく、就業規則や雇用契約書の不備が原因で、結果的に大きな経済的負担を余儀なくされた実例をお話した後の反応です。過去にトラブルを経験したことのない経営者ほど、「脅かされた」と思う度合いが強いようです。
ただ、経営者にとっては業界の慣習であったり、あるいは些細なことが、問題化した時点では想像を超えた事態になっていることがあるのは、まぎれもない事実です。正直、経営者に同情するケースもあります。また、そのような情報は、会社にとっては隠しておきたいことでもあるがゆえ、なかなか業界内からは伝わってこないこともあります。僕も含め多くの経営者が「仕事に集中したい」と思っているにもかかわらず、余計なことで頭を悩まされる、足を引っ張られるのは避けたいところですが、なかなかそうもいかないのも現実。「それも仕事、経営のうち」と思えればいいのですが、それもなかなか…。いかがでしょうか。(2014.12.4)
同伴手当・指名手当
その日、就業規則における指名手当、同伴手当の規定につき、頭を悩ませていた。規定の仕方により、割増手当の計算方法などが変わってくる。複数の労働基準監督署に確認をしてみても、ほぼ明確な回答がある一方、「2通りの考えがあります」「グレーゾーンです」といった回答も返ってくる。実際、トラブルになったところで、賃金台帳などと照合して、実態をもって判断するしかないというのが現状ともいえる。
おそらく、そこまできちんと整備された就業規則を作成しているクラブ関係の店は、ほとんどないだろう。だが、現実には、そこまで細かい点を追及されるケースが増えている。逆に言えば、そこまで細かく規定しないことには、予防法務の意味がない。また、クラブなど社交飲食店では、深夜割増手当の扱いも工夫が求められる。社労士の腕の見せ所? よかったら、当事務所まで問い合わせてみて下さい。